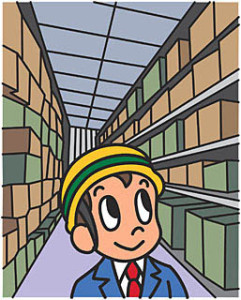[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
建設工事においては、500万円以上の工事(建築一式工事については1500万円以上等例外有り)の場合、建設業許可が必要になります。逆に、500万円未満の工事は「軽微な建設工事」として、建設業の許可がなくても請け負うことができます。
以前にも書きましたが、「軽微な建設工事」とは、次の工事を指します。
1)1件の請負代金が消費税込500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く)
2)1件の請負代金が消費税込1500万円未満の建築一式工事
3)主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供する、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事
ここで、請負金額の算定について問題になるわけです。なぜなら、大きな工事を2つに分けてしまえば請負金額が小さくなり、許可が不要になると考えられるためです。
しかし、以前にもお伝えしたとおり、これは通りません。
建設業法施行令1条の2において、次のとおり定められています。
(第2項)前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
〈第3項〉注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。
すなわち、工事の完成を(正当な理由なく)2つ以上の契約に分けてもダメですよ、ということと、材料が注文者から支給される場合はその材料費が含まれますよ、ということです。
また、この請負金額には消費税・地方消費税が含まれるとされています。
ちなみに、この「正当な理由」については、建設業法の適用を免れるための分割でないことを十分に証明できることが必要となるでしょう。実際には個別に行政庁の判断が出されることと思われます。
建設工事の単価契約(一日で終わるような工事)の場合においても、それが全体として一つの工事の完成を目的としている場合は、例え日々契約が行われ、その実績の集積が評価されているとしても、請負金額は全体を合算して判断されますので、「軽微な建設工事」に該当しなくなってしまう場合があります。ご注意ください。
以前にも書きましたが、許可を受けた種類の建設工事を行う際に、建設業者はその建設工事に附帯する工事については、施工することができるとされています。
これは、建設業法4条で、次のように規定されているためです。
(附帯工事)
第4条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
では、この「附帯工事」って何ですか、ということが次に問題となります。
附帯工事というのは、次のように言われています。
1)主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
2)主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
1)は例えば屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事など、主たる建設工事の機能を保全したり、能力を向上させるものをいいます。
2)は、天井の電灯を設置するための電気工事の施工に伴って必要となった内装仕上工事など、主たる建設工事に関連して余儀なく施工が必要となったものをいいます。
したがって、例えばA工事という工事名が見積書についていたとしても、工事の内容でB工事がメインの工事だったり、複数の工事が内訳として入っているような場合には、工事の種類としてAと認められない、ということも場合によってはあるわけです。
このとき、主たる建設工事がどちらか、ということは、上記の附帯工事の説明から結論づけられ、工事の名称や内訳金額の多寡などは参考とされるにとどまります。
このあたりが、やはりケースによって異なってきますので、なかなか一概には言えず、契約書等から総合的に判断されることになるため、実務上は即断が困難なところだと感じています。
ご参考になればと思います。
倉庫業の登録をするときに、まず最初にハードルとなるのは、建築基準法に適合した建物かどうか、というところです。
つまり、倉庫業の登録を受ける場合にはその前提として、建築基準法上違法な状態でないことが必要となります。
具体的には、建築確認の検査済証等がきちんとあるかどうか、というお話になるわけです。
なお、例えば工場などとして使っていた建物を用途変更して営業倉庫として使用するケースで、用途変更の場合は建築基準法に基づく完了検査は行われません。
したがって、この場合は、「倉庫業を営む倉庫」としての用途が確認できる、建築基準法に基づく確認済証等を添付させればよい、という運用がなされています。
今日は短いですが、ちょっとした倉庫業登録のポイントのご紹介でした!
建設業は、住宅からインフラまで、生活環境という側面で私たちの日常生活に大きく関わっている事業であると言えます。
特に事業の特性としては、一品物のため事前に品質を確認しづらいことや、多くの事業者が関わるのでマネジメントが必要になること、主に屋外・現地で行う生産活動であること等が挙げられるでしょう。
そんな中、建設業のクオリティを支える制度として、技術者制度というものが定められています。
今回はその技術者制度についてざっくりご紹介したいと思います。
御存知の通り、建設業の許可を受ける場合には、その要件の一つとして専任技術者の設置が求められています。
この「専任技術者」は、建設業法7条2号、15条2号に基づくもので、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、一定の要件に該当する方を充てなければいけないことになっています。
これは、建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行の確保を趣旨としていますので、基本的には契約締結業務を行う営業所(建設業法上の営業所)に常勤していなければなりません。
コレに対して、よく混同する概念として、配置技術者の制度があります。
建設業の許可業者は、請負金額の多寡にかかわらず、請け負った建設工事については必ず現場に「主任技術者」を置かなければなりません。
また、発注者から直接工事を請け負い、一定額以上を下請契約して工事を行う場合には、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません。
この、「主任技術者」「監理技術者」という制度は、建設業法26条に基づくものですが、名前がほぼかぶってる上に、なるための資格要件についても、許可の際の「専任技術者」と同じなので、よりいっそう混同してしまいがちです。
しかし、こちらの「主任技術者」「監理技術者」という制度の趣旨としては、工事現場において工事の施工がスムースに行くようにするためのものなのです。
さらにややこしくなるのですが、この「主任技術者」と「監理技術者」を「専任」させなければならない工事、があります。
それが、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(で政令で定めるもの)」です。
これは、細かくは建設業法施行令27条1項により定められていますが、個人住宅を除いた2500万円以上(建築一式工事の場合は5000万円以上)のもののほとんどの工事がその対象になっています。
そして、これらの現場の「主任技術者」「監理技術者」は「営業所の専任技術者」とは原則として兼ねることができません。
この辺の概念が、混同して分かりにくいので、よく整理していただくと良いかと思います。
建設業法上は、「建設業」とは「元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義しています。
つまり、いわゆる「請負契約」なのです。
請負契約とは、民法632条にあるように、
当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
契約のことを言います。
ここでポイントなのは、仕事を完成させる必要があることです。
仕事を完成させなければ、債務を履行したことにはならないので、その対価としての報酬を得ることはできません。
似た契約に、雇用契約や委任契約があります。
雇用契約は、同じく民法の623条に記載されています。
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
つまり、仕事を完成させることは契約の要素にはなっていないのです。
また、委任契約は民法643条に定められています。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
やっぱり、仕事の完成は契約の要素にはなっていません。
(写真は記事とは無関係です)
しかし、世の中には、いろいろなケースがあるわけで、常にちゃんとした契約書がある、というわけではありません。
タイトルと中身が乖離した契約書も、やっぱり実務上は結構見られます。
また、契約形態は取引に応じて千差万別なわけで、法律で定められている契約の形態しか許されないわけではありません。
したがって、単純な契約タイトルの間違いばかりではなく、業務委託契約とか、製作物供給契約とか、世の中にはいろいろな契約が存在しています。
ここで、建設業法が規制しているのが、「建設工事の請負契約」であるなら、契約書のタイトルを少し変える、いや、そもそもちょっと契約形態を工夫すれば建設業法の規制を免れて業務ができるのではないか、と考える人が現れても不思議ではありません。
そこで、建設業法では、24条で
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
と定めており、いかなる名称であっても、脱法行為を防ぐ目的で「建設工事の請負契約」とみなしますよ、ということを謳っているわけです。
というわけで、脱法行為はしないように気をつけましょう。
ちなみに、製作物供給契約により建設工事の完成を約する契約も規制は免れませんのでお気をつけください。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)
※Facebookページはこちら。
東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。
最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。
■取扱業務など■
・各種許可申請手続等
建設業、倉庫業、風営、自動車運送事業、動物関係手続、古物、探偵、開発行為、宅建、産廃、飲食、酒類販売、旅館、貸金、車庫証明、などなど。
・定款作成・法人設立
・外国人手続(ビザ等)
入管手続(ビザ、在留資格)、帰化申請、その他外国人関係手続(国際結婚・雇用等)
・契約書等書類作成
各種契約書・社内規則等作成
・相続(遺産分割協議書など)、遺言
・海事関係手続
★法務顧問
■ご依頼の流れ■
→こちらをご覧ください。
■費用報酬等一覧(例)■
→こちらをご覧ください。
■事務所所在地・連絡先等■
〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-16-8近代ビル6階
光永行政書士・海事代理士事務所/Office.MITSUNAGA
電話:03-5992-2758
FAX:03-5992-2502
■営業時間■
平日(月~金)午前10時~午後6時
※メールは随時受け付けております。
| 12 | 2026/01 | 02 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |