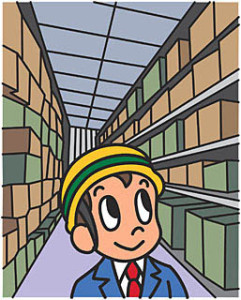[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
当たり前の話ですが、海上には陸にあるような3色信号機はありません。夜間航行などのときのために、船に取り付けなければならないライト(航海灯)などについては様々な決まりがあります。
今日はそんなところのお話です。
まず、航海灯ですが、海上衝突予防法で設置が義務付けられています。
船の大きさなどにより灯火の色や数が異なってくるのですが、基本的には、船の中心線上にマスト灯(白色)、左舷と右舷には舷灯(右舷が緑で左舷が赤)、船尾には船尾灯が設置されます。
全長50m以上の船(動力船)には、船の前部と後部にマスト灯をそれぞれ設け、後部の方を高くしなければなりません。
また、小型船などは全周灯で代用することも可能だったりと細かく定められています。
これによって、夜間などの視界が悪い時でも、船の方向がわかるようになっています。
また、船同士の衝突を防止するために、航法も定められています。
例えば、海上衝突予防法14条1項では、
2隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。(ただし書き以下略)
と定めており、これは、お互いに正面から進んできたときは、どちらも右に舵を切りましょう、ということです。
他にも、同15条では、
2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。(後半省略)
と定めており、進路が例えば90度の角度で交差するようなときは、相手の船が右に見える方が舵を右に切るなどして回避する義務がある、ということになります。
このように、船舶は基本的に右側通行、右側優先というルールになっています。
追い越しをするときも、原則として右側から追い越さなければなりません。
また、船の種類が異なる場合には、航行の自由度が低いほうが優先されることになっています。
すなわち、故障して運転ができないような船は回避しようがないので、優先度が高いことになります。
例えば、
優先度高←故障船などの運転不自由船>浚渫船など>操業中の漁船など>帆船>動力船→優先度低
のようになっています(優先度の低いほうが回避義務がある)。
いろいろ興味深いですね。
保健室の先生、というと皆さんいろいろと思い出がありそうな気がしてなりませんが、正直自分はあんまり覚えていません。
あまり大きな怪我などしたことがなかったからでしょうか。
保健室に出入りしている女の子の友達はいました。高校のときは保健室ではなく音楽室に出入りしていたのを今思い出しました。
とりあえず今日もそんなどうでもいい話題から入ってみました日曜の夜です。
保健室の先生は、法律的には「養護教諭」といいます。
養護教諭は学校教育法37条12項に根拠があり、必ず置かなければならない職とされています(ただし、養護をつかさどる主幹教諭が置かれている場合は置かなくても良い)。
養護教諭は「児童の養護をつかさどる」とされており、養護とは「児童生徒の健康を保護し、その成長を助けること」とされています。
ちなみに、保健室というのは学校保健安全法7条により「健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため」に設けられています。
多くの場合、養護教諭は「保健主事」(主事や主任に関してはいずれ別のエントリで)も兼ねており、学校の保健に関する事項の管理を担当しています。
戦前の「学校看護婦」から始まっているとのことですが、養護教諭の免許状が必要とされています。
児童生徒の身体面のほか、学校での健康管理や衛生管理、傷病対応などで役割を果たしてきましたが、平成20年に学校保健法が学校保健安全法に改正され、新たに「保健指導」という役割を担うことになりました。
学校保健安全法9条(保健指導)
養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。第24条及び第30条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
ココでのポイントは、、学級活動や学校行事などの場合の集団を対象とした従来のものではなく、個別の指導が求められるようになった、というところです。
1980年代以降のいじめや不登校の増加から、「保健室登校」などのキーワードにも分かるように、心の問題をサポートする役割を保健室は果たすようになってきました。
養護教諭にも、カウンセリング能力やメンタルヘルスに関する知識などが必要とされるようになり、今後よりいっそうの活躍が期待されています。
・・・ちょっとマジメな感じで締めてみました。
遺言の方法には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言、がありますが、目の見えない方にとって、前の2つは実質的に作成が困難かと思われます。
したがって、一般的には公正証書遺言の方法を選択することになるでしょう。
この場合も、遺言者の署名ができないのではないか、という心配があるかと思いますが、公証人法39条4項で、公証人は嘱託人(公正証書を作成して欲しいとお願いする人のこと)が署名できない場合に、その旨を記載して押印することができることになっています。
さらに、民法969条4号でも、公正証書遺言において遺言者が署名できないときは、公証人が事由を付記して署名に代えることができる、とされています。
実務上は、公証人が遺言者の氏名を代署し、署名できない理由を付記して職印を押印する、という処理になっているようです。
ちなみに、公証人法30条において、遺言にかぎらず公正証書の嘱託人が目の見えない方の場合、立会人の立会が必要とされていますが、公正証書遺言の証人2名とこの立会人は兼ねることができるため、別に立会人を用意する必要はありません。
なお、「口のきけない者」「耳が聞こえない者」については、民法969条の2において定められています。
(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
つまり、「口がきけない者」「耳が聞こえない者」は通訳人を介して遺言を行う、ということになります。
倉庫業の登録をするときに、まず最初にハードルとなるのは、建築基準法に適合した建物かどうか、というところです。
つまり、倉庫業の登録を受ける場合にはその前提として、建築基準法上違法な状態でないことが必要となります。
具体的には、建築確認の検査済証等がきちんとあるかどうか、というお話になるわけです。
なお、例えば工場などとして使っていた建物を用途変更して営業倉庫として使用するケースで、用途変更の場合は建築基準法に基づく完了検査は行われません。
したがって、この場合は、「倉庫業を営む倉庫」としての用途が確認できる、建築基準法に基づく確認済証等を添付させればよい、という運用がなされています。
今日は短いですが、ちょっとした倉庫業登録のポイントのご紹介でした!
建設業は、住宅からインフラまで、生活環境という側面で私たちの日常生活に大きく関わっている事業であると言えます。
特に事業の特性としては、一品物のため事前に品質を確認しづらいことや、多くの事業者が関わるのでマネジメントが必要になること、主に屋外・現地で行う生産活動であること等が挙げられるでしょう。
そんな中、建設業のクオリティを支える制度として、技術者制度というものが定められています。
今回はその技術者制度についてざっくりご紹介したいと思います。
御存知の通り、建設業の許可を受ける場合には、その要件の一つとして専任技術者の設置が求められています。
この「専任技術者」は、建設業法7条2号、15条2号に基づくもので、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、一定の要件に該当する方を充てなければいけないことになっています。
これは、建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行の確保を趣旨としていますので、基本的には契約締結業務を行う営業所(建設業法上の営業所)に常勤していなければなりません。
コレに対して、よく混同する概念として、配置技術者の制度があります。
建設業の許可業者は、請負金額の多寡にかかわらず、請け負った建設工事については必ず現場に「主任技術者」を置かなければなりません。
また、発注者から直接工事を請け負い、一定額以上を下請契約して工事を行う場合には、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません。
この、「主任技術者」「監理技術者」という制度は、建設業法26条に基づくものですが、名前がほぼかぶってる上に、なるための資格要件についても、許可の際の「専任技術者」と同じなので、よりいっそう混同してしまいがちです。
しかし、こちらの「主任技術者」「監理技術者」という制度の趣旨としては、工事現場において工事の施工がスムースに行くようにするためのものなのです。
さらにややこしくなるのですが、この「主任技術者」と「監理技術者」を「専任」させなければならない工事、があります。
それが、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(で政令で定めるもの)」です。
これは、細かくは建設業法施行令27条1項により定められていますが、個人住宅を除いた2500万円以上(建築一式工事の場合は5000万円以上)のもののほとんどの工事がその対象になっています。
そして、これらの現場の「主任技術者」「監理技術者」は「営業所の専任技術者」とは原則として兼ねることができません。
この辺の概念が、混同して分かりにくいので、よく整理していただくと良いかと思います。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)
※Facebookページはこちら。
東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。
最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。
■取扱業務など■
・各種許可申請手続等
建設業、倉庫業、風営、自動車運送事業、動物関係手続、古物、探偵、開発行為、宅建、産廃、飲食、酒類販売、旅館、貸金、車庫証明、などなど。
・定款作成・法人設立
・外国人手続(ビザ等)
入管手続(ビザ、在留資格)、帰化申請、その他外国人関係手続(国際結婚・雇用等)
・契約書等書類作成
各種契約書・社内規則等作成
・相続(遺産分割協議書など)、遺言
・海事関係手続
★法務顧問
■ご依頼の流れ■
→こちらをご覧ください。
■費用報酬等一覧(例)■
→こちらをご覧ください。
■事務所所在地・連絡先等■
〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-16-8近代ビル6階
光永行政書士・海事代理士事務所/Office.MITSUNAGA
電話:03-5992-2758
FAX:03-5992-2502
■営業時間■
平日(月~金)午前10時~午後6時
※メールは随時受け付けております。
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |